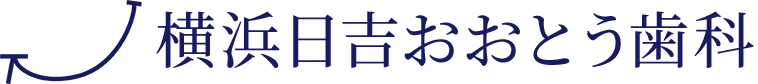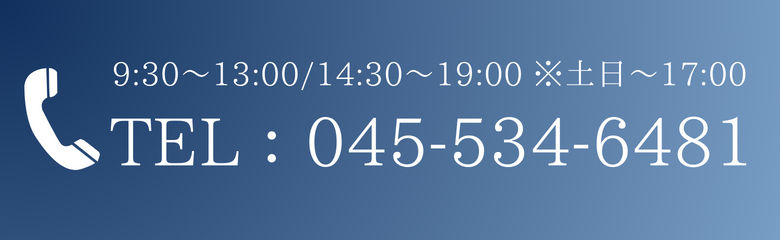目次
- インプラントが向いていない人の特徴
- インプラントが向いていない生活習慣
- インプラントが向いている人との違い
- インプラント以外の選択肢
- インプラント治療を受けるためにできること
- インプラントと代替治療の比較
- インプラント治療のリスクと注意点
- インプラントを長持ちさせるためのポイント
- まとめ
横浜市日吉の歯医者・歯科「横浜日吉おおとう歯科」です。
「インプラント治療を考えているけれど、自分に合っているのかわからない」と悩んでいませんか。
インプラントは天然歯に近い機能を持つ治療法ですが、すべての人に適しているわけではありません。
特に、以下のような方は注意が必要です。
- 顎の骨が足りない人(骨の量が不足している)
- 全身疾患を持っている人(糖尿病や高血圧など)
- メンテナンスを続けるのが難しい人(歯磨きや定期検診が苦手)
- 喫煙習慣がある人(インプラントの定着率が低下)
インプラントに向かない人の特徴とその理由を詳しく解説します。
また、向いていない場合の代替治療や、インプラントを受けるために必要な準備についてもご紹介します。
この記事を読めば、自分がインプラントに適しているかどうかを判断でき、最適な治療法を選ぶための参考になるでしょう。
インプラントが向いていない人の特徴
骨量が不足している(骨密度が低い)
インプラントは顎の骨に埋め込んで固定する治療法のため、骨の量が十分でないと安定せず、成功率が下がります。
特に、歯を失ってから長期間放置すると骨吸収が進み、インプラントを埋め込むための土台が確保できなくなります。
骨密度が低い状態で無理にインプラントを行うと、時間が経つにつれてぐらついたり、最悪の場合抜け落ちたりするリスクが高まります。
こうした問題を解決するために、骨造成(GBR)やサイナスリフト、ソケットリフトといった骨を増やす治療を併用することが可能ですが、追加の治療費や治療期間が必要になります。
歯周病が進行している
歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨が徐々に溶けてしまうため、インプラントを安定させるのが難しくなります。
さらに、歯周病菌はインプラント治療後の「インプラント周囲炎」を引き起こしやすく、放置するとインプラントが抜け落ちる原因となります。
歯周病の進行度によっては、インプラント治療を受ける前に歯周病の治療を完了させる必要があります。
軽度の歯周病であれば治療後にインプラントが可能になりますが、重度の場合は骨の吸収が進んでいるため、骨造成を含めた追加治療が必要になるケースもあります。
糖尿病や高血圧などの持病がある
糖尿病の人は傷の治りが遅く、感染症のリスクが高いため、インプラント手術後の回復がスムーズに進まないことがあります。
特に、血糖値が適切にコントロールされていない場合、手術後の傷口が化膿しやすく、インプラントの定着が妨げられる可能性があります。
また、高血圧の人は手術時の血圧上昇によるリスクが高く、心臓病や腎臓病を抱えている場合も、術後の経過が悪化しやすいため、慎重な判断が求められます。
持病がある人は、事前に内科医と相談し、インプラント治療を受けても問題がないか確認することが重要です。
インプラントが向いていない生活習慣
喫煙者はリスクが高い
タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は血管を収縮させ、血流を悪化させるため、インプラントと骨が結合する過程(オッセオインテグレーション)を妨げます。
その結果、インプラントが骨としっかり結びつかず、脱落しやすくなります。
また、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病のリスクが2倍以上高いとされており、インプラント周囲炎の発生率も高まるため、長期間の安定性が損なわれます。
インプラント治療を検討している場合、手術前後に禁煙することが強く推奨されますが、可能であれば完全に禁煙するのが望ましいでしょう。
歯磨きや定期メンテナンスをしない人
インプラントは人工歯のため虫歯にはなりませんが、歯周病と同じように「インプラント周囲炎」を発症するリスクがあります。
これは、歯茎の炎症によってインプラントを支える骨が溶けてしまう病気で、進行するとインプラントが抜け落ちる可能性があります。
日常の歯磨きが不十分な人や、定期的な歯科検診を受けない人は、インプラントの寿命を縮める原因になります。
特に、インプラントは天然歯よりも汚れが付着しやすいため、適切なブラッシングやデンタルフロス、歯間ブラシを使用することが重要です。
インプラントが向いている人との違い
インプラントが向いている人の特徴
インプラントが成功しやすい人の特徴として、以下のような点が挙げられます。
- 顎の骨が十分にある
- 歯周病がない
- 禁煙している
- 定期的なメンテナンスを行える
- 健康状態が安定している
こうした条件を満たしている人は、インプラント治療の成功率が高く、長期的に快適に使用できる可能性が高まります。
向かない人が治療を受けるために必要な条件
インプラントが向かないとされる人でも、適切な準備や治療を行うことで、インプラント治療を受けることが可能になる場合があります。
例えば、骨量が不足している場合は骨造成手術を受ける、歯周病がある場合は歯周病治療を完了させる、喫煙している場合は禁煙する、糖尿病などの持病がある場合は医師と相談して血糖コントロールを徹底するといった対策が有効です。
インプラント以外の選択肢
入れ歯(義歯)
入れ歯は、インプラントが向いていない人にとって最も一般的な選択肢の一つです。
部分入れ歯と総入れ歯の2種類があり、残っている歯の状態によって適したタイプが選ばれます。
入れ歯は手術を必要とせず、保険適用の範囲内で治療が可能なため、経済的な負担が少ないというメリットがあります。
しかし、使用中に違和感を感じやすく、噛む力が天然の歯に比べて大幅に低下するため、食事の際に不便を感じることがある点がデメリットです。
また、毎日のメンテナンスが必要であり、長期間使用すると歯茎や顎の骨が痩せてしまうリスクもあります。
ブリッジ
ブリッジは、失った歯の両隣の健康な歯を削り、そこに人工歯を固定する治療法です。
固定式で違和感が少なく、インプラントと比較すると治療期間が短いのがメリットです。
また、保険適用のブリッジであれば比較的安価に治療が可能です。
しかし、健康な歯を削る必要があるため、将来的にその歯の寿命を縮める可能性がある点がデメリットとして挙げられます。
また、支えとなる歯に負担がかかるため、噛み合わせのバランスが崩れることもあります。
ミニインプラント
ミニインプラントは、通常のインプラントよりも細い人工歯根を用いる治療法で、骨量が不足している人でも適用されることがあります。
手術の負担が少なく、比較的短期間で治療を完了できるのが特徴です。
ただし、通常のインプラントと比べると耐久性が低く、噛む力が十分に回復しない可能性があるため、適用できるケースは限られます。
インプラント治療を受けるためにできること
骨造成治療を受ける
インプラントを希望しているものの、骨量が不足している場合は、骨造成治療(GBRやサイナスリフトなど)を行うことで、インプラント治療が可能になるケースがあります。
骨造成には数カ月の治療期間が必要ですが、これによってインプラントの成功率を高めることができます。
ただし、追加の手術費用がかかるため、費用面の負担が大きくなることは考慮すべきポイントです。
歯周病を治療する
歯周病が原因でインプラントが向かないと診断された場合、まずは歯周病の治療を徹底することが大切です。
歯石の除去や歯周ポケットの洗浄を行い、炎症が落ち着いてからインプラント治療を検討することができます。
また、歯周病の再発を防ぐためにも、日々の歯磨きや定期的なメンテナンスを心がけることが重要です。
禁煙する
喫煙はインプラントの成功率を大きく左右する要因の一つです。
喫煙者は血流が悪くなることでインプラントが骨と結合しにくくなり、インプラント周囲炎のリスクも高まります。
そのため、インプラントを希望する場合は、手術の数カ月前から禁煙することが推奨されます。
生活習慣を改善する
糖尿病や高血圧などの持病がある人は、まずは主治医と相談しながら血糖値や血圧の管理を徹底することが重要です。
特に糖尿病の場合、血糖値が安定していればインプラント治療が可能になるケースもあります。
また、バランスの取れた食生活や適度な運動を取り入れることで、健康状態を改善し、インプラント治療の成功率を高めることができます。
インプラントと代替治療の比較
どの治療法が適しているか?
インプラント・ブリッジ・入れ歯のそれぞれの治療法にはメリットとデメリットがあり、患者の口腔状態やライフスタイルによって適した治療法は異なります。
しっかり噛みたい、見た目を重視したい人はインプラント、健康な歯を削りたくない人は入れ歯、短期間で治療を終えたい人はブリッジが向いているといえます。
事前のカウンセリングが重要
インプラント治療を検討している人は、まずは歯科医師とのカウンセリングを受け、口腔内の状態を詳しく診断してもらうことが重要です。
CTスキャンを用いた精密検査を行い、骨量や歯周組織の健康状態を確認することで、最適な治療方法を決定できます。
また、複数の歯科医院でセカンドオピニオンを受けることで、より適切な治療法を見極めることができます。
インプラント治療のリスクと注意点
インプラント周囲炎のリスク
インプラントは虫歯にはなりませんが、適切なケアを怠ると「インプラント周囲炎」という歯周病に似た病気を引き起こす可能性があります。
インプラント周囲炎は、インプラントの周囲に細菌が繁殖し、歯茎や顎の骨に炎症を起こす病気です。
進行するとインプラントがぐらついたり、最悪の場合は脱落することもあります。
特に喫煙者や糖尿病患者はリスクが高いため、口腔内の清潔を保つことが不可欠です。
噛み合わせの変化
インプラントは天然歯とは異なり、歯根膜を持たないため、噛み合わせのバランスが変化することがあります。
適切な噛み合わせが保たれていないと、顎関節症のリスクが高まったり、周囲の歯に負担がかかることがあります。
そのため、治療後も定期的に噛み合わせをチェックし、必要に応じて調整することが大切です。
外科手術のリスク
インプラント治療は外科手術を伴うため、術後の腫れや痛み、出血などのリスクがあります。
また、骨が十分に回復しないうちにインプラントを使用すると、骨との結合が不完全になり、インプラントが定着しない可能性もあります。
治療後は無理に硬い食べ物を噛まないよう注意し、歯科医師の指示に従って慎重にケアすることが重要です。
インプラントを長持ちさせるためのポイント
定期的なメンテナンスを受ける
インプラントを長く使い続けるためには、定期的な歯科検診が必須です。
インプラント周囲炎の早期発見や、噛み合わせの調整を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
一般的には3〜6カ月に1回の定期検診が推奨されており、歯科医院でのプロフェッショナルクリーニング(PMTC)を受けることで、口腔内の健康を維持できます。
正しいブラッシングを習慣化する
インプラント周囲炎を防ぐためには、毎日の歯磨きが欠かせません。
特にインプラントの周囲は歯垢がたまりやすいため、専用の歯ブラシやデンタルフロスを使い、丁寧に清掃することが重要です。
電動歯ブラシを活用するのも効果的で、歯科医院で正しいブラッシング方法を指導してもらうとよいでしょう。
噛み合わせのチェックを定期的に行う
インプラント治療後は、時間の経過とともに噛み合わせが変化することがあります。
特に、食いしばりや歯ぎしりの癖がある人は、インプラントや周囲の歯に負担がかかり、トラブルを引き起こす可能性があります。
ナイトガード(マウスピース)を装着することで、歯やインプラントへの負担を軽減できるため、必要に応じて歯科医師に相談するとよいでしょう。
生活習慣の改善
喫煙や不規則な生活は、インプラントの寿命を縮める原因となります。
タバコを吸うと血流が悪くなり、インプラントの定着が妨げられるため、禁煙が推奨されます。
また、糖尿病の人は血糖値のコントロールを徹底し、口腔内の健康管理に努めることが大切です。
まとめ
インプラントは天然歯に近い機能を持つ優れた治療法ですが、全ての人に適しているわけではありません。
持病がある人、骨量が不足している人、メンテナンスが難しい人などは、インプラント以外の選択肢を検討する必要があります。
入れ歯やブリッジなどの代替治療も、それぞれメリット・デメリットがあるため、自分の口腔状態やライフスタイルに合った治療法を選ぶことが重要です。
インプラント治療を受ける場合は、リスクを理解した上で、適切なケアと定期的なメンテナンスを継続することで、長期間快適に使用することができます。
自分に合った治療法を見つけるためにも、信頼できる歯科医師と相談しながら、最適な選択をしましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。

大藤 竜樹 | Ohto Tatsuki
日本大学歯学部 歯学研究科大学院卒業後、医療法人裕正会 イースト21デンタルオフィス、品川シーサイド歯科に勤務。院長就任後、医療法人大協組理事に就任。
2020年に横浜日吉おおとう歯科を開院。
【所属】
- ・日本歯科保存学会
- ・日本口腔インプラント学会
- ・日本顎咬合学会 認定医
- ・日本顎咬合学会関東甲信越支部理事
- ・OJ(Osseointegration Study Club of Japan)
- ・JCPG(日本臨床歯周療法集談会)理事
- ・5D-FST
【略歴】
横浜市の日吉駅徒歩5分の歯医者
『横浜日吉おおとう歯科』
住所:神奈川県横浜市港北区 箕輪町1-24-9 みのわメディカルビレッジ4F
TEL:045-534-6481